「二重埋没を受けたけれど、理想の二重にならずやり直したい」「時間が経つにつれて取れてしまい、再施術を受けたい」
そんな悩みを抱える方は少なくありません。
実は、二重埋没法はやり直し(再施術)が比較的しやすい施術であり、正しい知識と手順を踏めば再び理想の目元に近づけることが可能です。
一方で、やり直しにはタイミングやまぶたの負担、それに伴う回数の限界など、いくつかの注意点も存在します。
この記事では、埋没法のやり直しが「どこまで」「どのように」できるのかを、専門的な視点からわかりやすく解説。
さらに、やり直しを繰り返さないための方法や、再施術に強いクリニックの選び方も紹介しますので、二重埋没をやり直すべきかお悩みの方はぜひ参考にしてみてください。
二重埋没法のやり直しは可能?回数とタイミングを解説
埋没法のやり直しが可能な理由と回数の目安
埋没法は、まぶたを切開せずに医療用の糸で留めるだけで二重を形成する施術です。
このため、基本的には糸を外す(抜糸する)ことで元に戻すことができ、まぶたの組織も大きく傷つけない=やり直しがしやすいという特徴があります。
理論上は複数回の再施術が可能であり、仕上がりに満足できなかった場合や、時間の経過によってラインが薄くなった場合にも対応できます。
ただし、無限にやり直しができるわけではありません。
再施術を行うたびに、まぶた内部の組織には微細なダメージが蓄積します。
また、フォーエバークロスなどの複雑な留め方をしている場合、抜糸が難しかったり、ダメージが大きくなってしまったりする場合も。
そのため、一般的にはやり直しは3〜4回までにとどめるのが理想的とされています。
これを超えて何度も糸を通すと、まぶたの裏側の組織が硬くなったり、糸の跡が残ったり、思い通りのラインが作れなくなるリスクが高まります。
また、そもそもすぐに外れてしまったり何度やっても理想のデザインにならない場合には、埋没法が適していない可能性も高いので、切開法を検討した方がいい場合もあります。
再施術が可能なタイミング
再施術は、「受けたいと思った時期」にすぐ行えるわけではありません。
まぶたの腫れや炎症が残っている状態で再手術を行うと、糸の固定が不安定になったり、腫れや内出血が長引くリスクがあるためです。
一般的な目安として、前回の施術から1ヶ月以上は間を空けることが推奨されます。
多くのクリニックでは、まぶたの状態が安定する1〜2ヶ月前後を再施術の目安としています。
この期間で腫れやむくみが完全に落ち着くため、ラインの再設計がしやすくなります。
二重埋没をやり直す際の再施術方法と注意点
再施術を行う際には、まず前回の施術でまぶたに留めた糸をどう扱うかを確認する必要があります。
まぶたの状態や希望するラインの形によって、糸を抜く(抜糸)必要がある場合と、糸を残したまま再固定できる場合があります。
それぞれの方法にはメリットとリスクがあり、適した方法は人によって異なります。
以下では、抜糸の要否ごとの特徴と注意点を整理して解説します。
抜糸が必要なケース
抜糸とは、前回の埋没法でまぶた内部に留めた医療用の糸を取り除く処置です。
再施術の前に抜糸を行うことで、まぶた内部の状態をリセットし、新しいラインを設計しやすくなります。
抜糸が必要となる主なケース
- 現在の二重ラインを狭くしたい場合
- まったく新しいラインに変更したい場合
- 糸玉が目立つ、または目に違和感がある場合
- すでに複数回の埋没を行っており、まぶた内部に糸が残っている可能性が高い場合
抜糸を行うことで、まぶた内部をきれいな状態に戻し、再施術後のラインを安定させることができます。
ただし、まぶたの組織に一時的な負担がかかるため、前回の手術から2ヶ月程度の間隔を空けて行うのが理想的です。
また、抜糸には別途費用がかかることが多く、1点あたり1〜3万円前後が一般的な相場です。
できるだけ前回と同じ医師に依頼することで、糸の位置や構造を正確に把握したうえで安全に処置を進めることができます。
抜糸は“再施術の準備段階”と考えるのが適切です。
一度まぶたをリセットしてから新しいラインを形成することで、仕上がりの精度が高まります。
抜糸が不要なケース
まぶたの状態によっては、糸を抜かずに再施術を行うことも可能です。
この場合は、既存の糸をそのまま残したうえで、新しい糸を追加して二重ラインを作り直します。
抜糸が不要となる主なケース
- 現在の二重よりも幅を広げたい場合
- 既存の糸が完全に外れており、新しい糸のみで再形成できる場合
基本的に、ラインを広げる際は旧ライン(狭い位置)より上に新しい糸を留めるだけで済むため、
既存の糸を抜かなくても干渉せずに再施術できるケースが多いです。
ただし、まぶたの内部構造や糸の位置は個人差があり、
旧糸が浅い位置にあったり、癒着していたりする場合には、
抜糸をしてから行った方が安全・確実なケースもあります。
また、「抜糸の有無」や「施術方針」についてはクリニックや医師の考え方によって異なるため、再施術を検討する際は、事前に方針や理由をしっかり確認しておくことが大切です。
抜糸なしでの再施術は、ダウンタイムを短く抑えられる一方で、まぶたに糸が複数残ることによる違和感や炎症のリスクもあるため、慎重な判断が求められます。
再施術を安全に行うための注意点
再施術を行う際には、初回の施術情報(糸の本数・留め方・手術時期など)を医師に正確に伝えることが重要です。
まぶたの内部構造は個人差が大きく、初回の情報が不十分だと再施術の精度に影響する場合があります。
また、腫れや炎症が残っている状態で再施術を行うと、まぶたの癒着やラインの乱れが起こりやすくなります。
特に抜糸を伴う場合は、まぶたの回復を待ってから施術することで、組織への負担を最小限に抑えられます。
再施術後は、目をこすらない・過度な運動や飲酒を避ける・清潔を保つといった基本的なケアを守ることで、仕上がりの安定性と持続力を高めることができます。
埋没法のやり直しは「技術」と「タイミング」の両方が大切です。
まぶたの状態を見極めながら、医師と二人三脚で進める意識を持つことが成功への近道です。
やり直しを繰り返さないポイント
埋没法は、まぶたを切開しない手軽さが魅力ですが、糸によって二重を支える構造上、時間の経過や体質によって取れてしまうリスクを避けることはできません。
そのため、何度も再施術を繰り返してしまうケースも少なくありません。
しかし、やり直しを重ねるほどまぶたの負担は大きくなり、最終的に思い通りのラインが作りにくくなることもあります。
ここでは、再施術を繰り返さないために知っておきたい「切開法への切り替え」や「埋没法を長持ちさせる工夫」について解説します。
埋没法の適応を見極め、切開法も視野に入れる
埋没法が何度も取れてしまう場合、まぶたの構造的な理由が隠れていることがあります。
特に以下のような特徴がある方は、埋没法の効果が安定しにくいタイプです。
- まぶたが厚く、脂肪が多い
- 皮膚が伸びやすい
- 幅広い二重ラインを希望している
- 過去に3回以上の再施術を行っている
このような場合、無理に埋没法を繰り返すよりも、切開法に切り替えることで根本的な改善が期待できます。
切開法は、まぶたの皮膚を一部切開し、内部でしっかりと二重ラインを固定する施術です。
まぶたの厚みや脂肪量を調整しながら二重を形成するため、ラインが取れにくく、長期間安定した仕上がりを得やすい点が最大のメリットです。
切開法と埋没法の比較
切開法と埋没法はどちらも二重整形術ですが、それぞれ一長一短があります。
目的やライフスタイル、まぶたの状態に応じて選択肢を検討しましょう。
| 施術法 | 主な特徴 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 切開法 | まぶたを切開して内部でラインを固定する | ・効果が半永久的に持続する ・まぶたの脂肪やたるみも改善できる ・取れにくく再施術がほぼ不要 | ・ダウンタイムが長い(2週間〜1ヶ月) ・費用が高い(約20〜40万円) ・修正やデザイン変更が難しい |
| 埋没法 | 医療用の糸で二重を形成する(切らない施術) | ・施術が手軽でダウンタイムが短い ・修正ややり直しがしやすい ・微妙なライン調整が可能 | ・糸が取れる・緩むなど持続性に限界がある ・複数回行うとまぶた内部が硬くなるリスクがある |
仕上がりの持続性を重視するなら切開法、
手軽さや修正のしやすさを重視するなら埋没法が向いています。
埋没法を長持ちさせるための術後ケアと生活習慣
再施術や切開法を検討する前に、まずは今の二重を長持ちさせる工夫を意識しましょう。
埋没法の持続期間は、施術後のケアや日常習慣によっても大きく変わります。
- 目を強くこすらない・マッサージを避ける
→ 糸が緩んだり、まぶた内部の摩擦でラインが崩れる原因になります。 - クレンジングや洗顔時は優しく行う
→ 摩擦を減らすだけでも糸への負担が軽減されます。 - むくみを防ぐ生活習慣を意識する
→ 睡眠不足や塩分過多はまぶたの腫れを招き、ラインの安定を妨げます。 - 定期的なメンテナンス相談を行う
→ 違和感やラインの薄れを早期に発見できるため、再施術を防ぐことにつながります。
再施術で後悔しないためのクリニック選びのポイント
埋没法のやり直しは、初回手術よりも難易度が高くなります。
そのため、どのクリニック・どの医師に依頼するかが、仕上がりを左右する重要なポイントです。
「前回より自然な二重にしたい」「これで最後にしたい」と思うなら、
価格や立地だけでなく、経験・対応力・誠実さといった観点からクリニックを見極めることが欠かせません。
ここでは、再施術で後悔しないための4つの判断基準を紹介します。
①症例の多いクリニック・医師を選ぶ
再施術は、初回よりもまぶた内部の構造が複雑になっているため、医師の技術力や解剖学的な理解が結果を大きく左右します。
そのため、まず重視すべきは「症例数と実績」。
埋没法や修正手術の症例が多いクリニックほど、多様なまぶたのタイプに対応できる経験があります。
特に、修正や抜糸を伴う症例の実績が多い医師は、過去の手術による癒着や糸残りなどにも的確に対応できる傾向があります。
②カウンセリングが丁寧な医師を選ぶ
二重埋没においては、カウンセリングが最も重要な工程のひとつです。
理想のラインやまぶたの状態を細かく確認し、リスクや限界を明確に説明してくれる医師を選びましょう。
良いカウンセリングの特徴は以下の通りです。
- 希望のデザインに対して「可能か・難しいか」を正直に伝えてくれる
- 二重のラインのシミュレーションを複数パターンで行ってくれる
- まぶたの厚み・脂肪量などから、埋没法が適応かどうかをはっきりと言ってくれる
逆に、「すぐできます」「簡単に直せます」といった軽い説明しかない場合は注意が必要です。
誠実な医師ほど、手術の難易度や再発リスクも率直に伝えます。
また、初回に施術を受けたクリニックに不安がある場合は、
セカンドオピニオンを取ることも有効です。複数の視点で判断することで、最適な治療方針が見えてきます。
③口コミや評判、アフターケア体制のチェック
埋没法のやり直しでは、「術後のフォロー体制」が非常に重要です。
トラブルが起きた際にすぐ相談できる環境があるかどうかで、安心感も仕上がりも変わります。
チェックすべきポイントは以下の通りです。
- 口コミやSNSで実際の体験談を確認(成功例だけでなく、満足できなかった例も)
- トラブル時の対応方針(診察料・再施術費用など)
- 保証制度の有無と内容(適用条件や期間など)
保証制度は、ラインの取れ・緩みなど“明確な不具合”に限って適用されるのが一般的です。
「デザインを変えたい」などの希望は対象外であることが多いため、事前に保証の対象範囲を確認することがトラブル防止につながります。
④やり直しにかかる費用の確認
再施術では、抜糸費用と再施術費用の両方が発生する場合があります。
一般的な相場は以下の通りです。
- 抜糸費用:1点あたり約1〜3万円
- 再施術費用:片目で5〜15万円前後、両目で10〜30万円前後
初回施術に保証がついている場合、保証期間内であれば割引価格または無料で修正できるケースもあります。
ただし、保証内容はクリニックによって異なり、「保証が付いている=無料で直せる」わけではない点には注意が必要です。
保証の有無に関わらず、再施術を前提に費用を確認しておくことで、
「思ったより高額だった」と後悔するリスクを防げます。
埋没修正実績が豊富なMEMOTO CLINIC鈴木大路院長に二重埋没法のやり直しについて聞いてみました

埋没法の修正は、術前のデザインや糸の掛け方・皮膚の特性など、総合的に見極める必要があり、高度な経験が求められます。
二重埋没法の指導医としての経歴があるMEMOTO CLINICの鈴木大路院長に聞いてみました。
二重埋没法の相談に来る人にはどんな人が多いですか?
表向きのきっかけとして多いのは「糸が取れてしまった気がする」「二重ラインがだんだん薄くなってきた」というご相談です。
ただ、実際にまぶたを診察してみると、初回の手術の段階で十分に評価されていなかった「根本的な原因」を抱えている方がかなり多いと感じています。
よく見られるパターンは、大きく3つあります。
1つめは、そもそもまぶたの構造が埋没向きではなかったケースです。脂肪が厚かったり、皮膚がたるみ気味だったり、まぶたを持ち上げる筋肉(挙筋)が弱かったりする場合、本来は慎重な見極めが必要です。それにもかかわらず、構造をきちんと見ずに誰にでも同じ埋没法を行ってしまうと、数ヶ月〜1年ほどでラインが不安定になりやすくなります。
2つめは、前医での埋没が浅すぎる・弱すぎるケースです。最近は「痛くない」「腫れにくい」を押し出しているのクリニックも増えていますが、その裏で、かなり浅く・弱く糸を留めている埋没も見られます。その結果、数週間〜数ヶ月のうちにラインが緩んでしまい、再手術をご希望される方が来院されます。
3つめは、理想のデザインと実際のラインが合っていないケースです。二重幅自体は合っているのに目頭側だけ皮膚がかぶってしまったり、末広寄りにしたかったのに実際は平行っぽく見えたり、目を開けたときの食い込みが左右で違っていたり……。 こういった「なんとなく違う」という違和感は、カウンセリングの段階でデザインのすり合わせが十分にされていなかったことが原因なことが多いです。再手術をご希望の方は、ほとんどの方がミリ単位のズレを気にされていますね。
再手術の際、どのような点にこだわって治療方針を決めているのでしょうか?
MEMOTO CLINICでは、再手術を「糸をもう一度留め直すだけの処置」とは考えていません。
まずは「最初の埋没で何が起きていたのか」を医学的に整理することを一番大切にしています。
再手術で最も重要なのは、「なぜ取れたのか」をはっきりさせてからデザインを決めることです。糸そのものが緩んでいたのか、皮膚の厚みやたるみが邪魔をしていたのか、脂肪が多いのか、そもそも二重幅の設定に無理があったのか、こうした点を一つずつ確認し、原因を整理します。このステップを飛ばして、前回と同じような方法で再埋没をしても、ラインは長持ちしません。
埋没だけでは対応が難しいケースでは、どのような工夫をされていますか?
構造的な問題が強い場合は、埋没単独よりも[埋没+α」にしたほうが、ラインの安定感が大きく変わります。
脂肪が厚い方には『脱脂』、皮膚の余りが気になる方には「眉下切開」や「二重幅の調整」、挙筋が弱い方には「眼瞼下垂手術」など、必要に応じて補助的な処置を組み合わせることがあります。
できれば埋没だけでどうにかしたいというお気持ちはよく分かります。その上で、構造的に難しいケースでは、無理をして埋没だけをおすすめするのではなく、「埋没+α」という選択肢も含めてお話しするようにしています。
再手術ならではの難しさや、特に意識しているポイントはどこでしょうか?
再手術が難しい理由のひとつは、前回のラインによる癖・瘢痕・折れグセが必ず影響するという点です。初めての二重整形と比べると自由度が下がるので、どの癖をあえて活かすか、どの癖はできるだけ目立たないようにするかを見極めながらデザインしていきます。同じ再手術でも、患者様ごとに残っている癖はまったく違うため、完全にオーダーメイドで留める位置やデザインを細かく微調整していきます。
また、再手術をご希望される方は、初回のとき以上に左右差に敏感です。1mmの違いでも印象が変わるため、仕上げの調整には特に時間をかけています。目の開き方、筋肉の動き、皮膚の重なり方、光が入る向き・量といった細かい点まで確認しながら、最終的なバランスを整えます。この繊細な調整は、目元に特化しているクリニックだからこそ、日々の経験を活かして行える部分だと考えています。
まとめ|理想の二重を取り戻すために知っておきたいポイント
二重埋没法は、切開を伴わずに自然な二重を作れる人気の施術ですが、時間の経過や体質によってラインが薄くなったり、取れてしまうことがあります。
ただし、埋没法は比較的やり直しがしやすい施術であり、まぶたの状態を見極めて正しい方法を選べば、再び理想のラインを取り戻すことも可能です。
再施術を検討する際に押さえておきたいポイントは、次の4つです。
- やり直しは3〜4回までが理想的
まぶたの負担を考慮し、繰り返しすぎないことが大切です。 - タイミングは1〜2ヶ月空けてから
腫れや炎症が完全に落ち着いてから再施術を検討しましょう。 - 抜糸の有無はケースバイケース
ラインの変更内容やまぶたの状態によって、医師が適切に判断します。 - 再施術を繰り返すより“安定した選択”を
取れやすい体質や複数回の修正を経た場合は、切開法も検討に値します。
また、どの方法を選ぶにしても、信頼できるクリニックと医師を選ぶことが最も重要です。
症例数や技術力、カウンセリングの丁寧さ、保証制度の内容など、複数の視点から比較し、納得できる環境で施術を受けましょう。
今回は埋没法の再手術が必要になる理由から、再手術ならではの難しさ、そしてMEMOTO CLINICで大切にされているこだわりまで、鈴木先生に丁寧に解説していただきました。
再手術は不安を抱えた状態でご相談に来られる方が多い分、細やかな診察と原因の見極めが、理想の二重ラインへ近づくための大切なステップになります。
鈴木先生、貴重なお話をありがとうございました。
この記事の監修医師

MEMOTO CLINIC院長 鈴木大路
経歴
- 名古屋大学医学部卒業
- 豊田厚生病院
- 大手美容外科 岐阜院院長
- 大手美容外科 金沢院院長
- 大手美容外科 浜松院院長
- 大手美容外科 二重埋没法指導医
得意施術
- 目元整形全般
- 二重整形
- クマ取り
- 目尻切開
- グラマラスライン形成
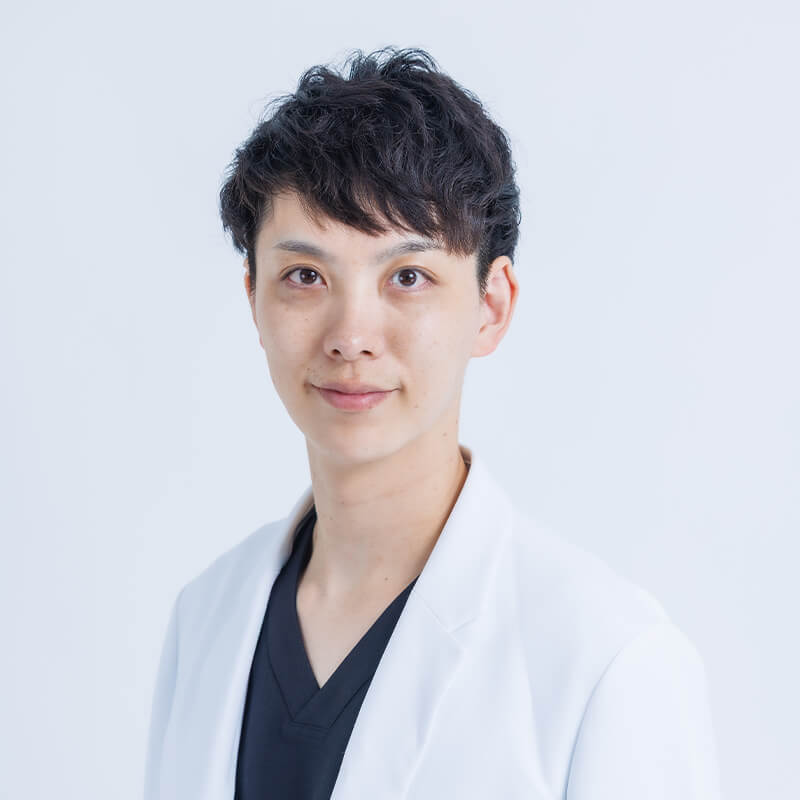
コアクリニック院長 江崎正俊
経歴
- 名古屋大学医学部医学科卒
- 大手美容外科 院長歴任
- eクリニック西日本統括医師
得意施術
- 鼻整形
- クマ治療
- 目尻切開
- グラマラスライン形成
- 人中短縮

